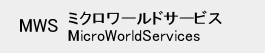
本日の画像
ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。
日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します
ミクロワールドサービスが顕微鏡の世界を伝えるコーナーです。
日々の業務メモやちょっとした記事もここに記します
【2026年】 1月 2月
【2025年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2024年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2023年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2022年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2021年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2020年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2019年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2018年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2017年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2016年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2015年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2014年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2013年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2012年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2011年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2010年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2009年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2008年】 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【2007年】 9月 10月 11月 12月
【今月にもどる】
おしらせ
引き続き休みを継続します。業務内容見直し中につき再開時期は未定とさせていただきます。2026/02/01
おしらせ その2
内部的な業務は日常行っています。体調も問題なく睡眠もとれておりトラブルのない日々を過ごしていますが,今後どのように仕事をするべきか考えています。業態の見直しも進めております。メールなどは問題なく作業できますので連絡事項などある方はメールいただけますと幸いです。新規業務の話とか,体調不良関連の話はご遠慮願います。
それから重要なこととして一件。Gmailご利用の方は,できれば別のアドレスから送信願いたいところです。さくらインターネットからGmailへ送信すると不着のトラブルが多く,現在も続いています。SPF設定などを見直しても,ある方には即時で届きある方には一日かかる,ある方には届かないといったグチャグチャな事象となっています。こちらから対応できることはこれ以上はなさそうなのでお願いする次第です。
どうぞよろしくお願いたします 2026/02/01
2026年2月28日

きょうも習熟運用。ライブセルイメージングをDICで。あり合わせの組合せで運用しているので,それにより生じる収差を補償するような作業が必要です。光学的に補償(コンペン)できることもありますし,デジタル処理で補償することもあります。どちらにしても像品質は向上します。何もしなければ,本ページ的には,ぐだぐだの使えない像になります。そうならないようなこだわりがだいじな気もします(画像/MWS)。
2026年2月27日

バルコニーの別のカップはこんな具合。いっしょに写っているバクテリアからわかるように,こちらは微少なニッチアが増殖中です。夜間から明け方は数度,昼は15度くらいになる過酷な環境ですが元気に増殖しています。できれば大型珪藻を自宅で増やしたいところですがまだ成功していません。その理由は,まじめに取り組んでいないからです…。原因はわかっているのです…。わはは(画像/MWS)。
2026年2月26日


この1ヶ月以上,イメージングのテスト物体の追求と,各種コントラスト法によるによるイメージング,ライブセルイメージングの日々が続いています。やってみると実りがあるもので,はじめて見る物体を目にして,不足している条件を秒で見抜き,次々と実装して試験。そして数時間,あるいは数日後には追い込まれた整った像が出てくるという感じです。こういった習熟訓練は,年に1回はやらないといけない気がします。使用する光学素子の数は数十を超えるのでその組合せを身体で覚える必要があるのです。。
きょうの画像はバルコニーの100mlほどのカップで育てている珪藻たち。冬場は珪藻の生育に適していて都会のマンションでもちゃんと増殖します。ただ,小型種のみです。きょうの画像も液浸対物領域のとても小さなものです。画像1枚目に写っているバクテリアに気付いた人は,この珪藻の小ささがわかるでしょう(画像/MWS)。
2026年2月25日



ことしに入ってから3回目のウマヅラカワハギ。カミさんがぶら下げて帰ってきて,30分後に煮魚にして献上したところ「学習」が行われたらしく,ウマヅラに値引きシールが貼られていると入荷します。一人分で150円のウマヅラなので,東京都心の立地を考えれば格安でタダみたいなもんです。
それで3回も入荷すると料理長の筆者も「学習」します。味を煮含める時間が最小限なので調理法を工夫するわけです。ウマヅラは劣化を感じなければ洗わずそのまま身に切り込みを入れて,盛り付けたときの上面を下にしてフライパンに入れます。そこにしょう油を適量注ぎます。ショウガをほんの少し加えて,そのまま15分ほど置きます。それから日本酒を加えて強火で加熱します。フタはしますが落とし蓋はしません。吹きこぼれるようになったら火力を落として吹きこぼれない限界付近にします。これで5分ほど煮ます。
そうしたらフタを外して強火で煮汁を飛ばします。煮汁にとろみがついてツメになるくらいのところで火をとめてフタをして鍋止めします。
盛り付けは当然,魚をひっくり返して左に頭,右に尾がくるようにします。残ったわずかな煮汁を回しがけます。これで完成。画像2枚目です。これで全部の煮汁がかかっています。
この方法によれば,落とし蓋も必要なく,盛り付けた上面には味が染みていて,そして盛り付けたあとに下面は煮汁で味がつくのです。そしてたっぷりの煮汁で魚をだしがらにするような煮魚ではなく,少量の酒しょうゆで蒸すことによりうまみは保持され,煮汁もツメとして機能するので無駄がありません。もちろん煮汁も余すことなくいただきます。ごはんが進む進むw
さて身離れがよいカワハギですから,きれいな骨が残ります。これは取っておいて,関節を一つずつポキポキ折って,湯飲みに入れて電子レンジでチンします。そこに日本酒を注いでさらに電子レンジチンして沸騰させます。フタをしてしばらく置いてから着火してアルコールを飛ばします。そこに適量の日本酒を注いで味を調節してカワハギの骨酒のできあがり。同じことを繰り返して2杯までいけます。深いうまみを感じる味わいです。こうして300円ちょいのカワハギ2匹は骨の髄まで有効利用されたのでした(画像/MWS)。
2026年2月24日


ことしも可愛い子たちとの触れ合いの機会をいただきました。いつもお世話になっている先生と,いつも出てきてくれるケロちゃんたちに感謝です。大自然の営みをみているとなんだか心が安らぐのです(画像/MWS)。
2026年2月23日




みえるはずの構造を消してしまう,という欠陥をもつのが微分干渉法です。そのことを示したのがきょうの画像の最初の2枚。微分干渉法は2本の偏光ビームの光路差をコントラストに変換しているわけですが,ビームが2本ということは解像に方向性があるのです。2本のビームがうまく段差を通過すれば段差の光路差によってビームに位相差が生じ微分干渉光学系の結果として明暗のコントラストを生じます。しかし2本のビームが段差を通過しないような条件では,位相差も生じないのでコントラストも生じません。このため,微分干渉検鏡では,偏光ビームの方向性(シャー)に対して物体を最適に配置するために回転ステージを使うのが最善です。
…と書きましたが微分干渉法で回転ステージを使いこなしている人はあまり見かけません。。メーカーさんも微分干渉法の高価な顕微鏡なのに固定ステージを供給していたりします。それはそれでいいとして,説明書には「これでは不十分です」と書いてあるのだろうか…。気になります。生細胞などはもともとコントラストが小さいので,微分干渉でも最適なシャーを与えないと見えない構造などいくらでもあります。つまりは回転ステージがなければ消えてしまう構造などいくらでもあるのです。
まぁ,そこいらへんの大学や研究所で微分干渉だけを使っておられる方々は多いのです。本人としては何も知らないのですから仕方のないことかもしれませんが,存在する構造を消して不自然な像にしているかもという自覚は常に持っていて欲しいものです。
きょうの画像3,4枚目は同じ物体の位相差像。DLレンズによるものです。この像を見ると,珪藻被殻1枚の中に,高屈折率部分と思える骨格が走っていて,そこに乗るように胞紋が開いています。もちろん位相差法に方向性はないので物体を回転しても像のコントラストに変化はありません。この観察結果からでも,論文ネタになりそうな面白いテーマが潜んでいる感じがするのですが,まぁ,あらゆるものを固定ステージの微分干渉観察で済ませている方々には,こんなわかりやすい像の違いが見えているのかしらと思ったりもします(画像/MWS)。
2026年2月22日

この珪藻被殻は上の殻と下の殻をつなぎとめるガードルバンドの部分。丸い筒状の一部です。もちろんガラス質なのですがきわめて薄く曲げて伸ばすことができます。筒の一部なので伸ばせば平面となるのでバキバキに割れたりはしません。NA=0.8以上で見えてくる適度なサイズの微細構造があるのでテスト用にも向いています。低NAの暗視野ではひじょうに鮮明なブルーに輝きます(画像/MWS)。
2026年2月21日

きょうの画像は珪藻土から分離した謎の珪藻被殻。とても薄く破片しか出土しませんので全体像はわかりません。たぶんコアミケイソウみたいな円筒形だろうと想像します。この珪藻被殻は薄っぺらいので押しつぶして展開図のようにすることが(うまくいけば)できます。珪藻を押し葉のようにするわけなのですが,適当な破片を拾って押しつぶす操作の困難さは言語に絶します。ほんとうに押しつぶせば粉々になるので,封入剤の固化後の膜厚を予想してぴったり珪藻被殻の厚みになるように調節するといった感じです。
このような操作によってきょうの画像は筒の側面部分に位置する構造が一枚撮りのピント平面に収まっています。はじめて見る風景です。この世のものとは思えない何かを感じます(画像/MWS)。
2026年2月20日


きょうの画像はクモノスケイソウの薄い被殻。細胞分裂初期のもので,まず骨格からできあがることがよくわかります。被殻はひじょうに薄く,透過明視野ではほとんど見えません。微分干渉では画像1枚目のように見えます。位相差(DLL)では画像2枚目のようになります。微分干渉像ではコントラストが低く,物体のコントラストに方向性があります。位相差像は高コントラストで方向性がなく構造が把握しやすいように見えます。こういった像特性を把握していれば,未知の物体を見たときに適切な検鏡法にたどり着ける可能性が高まります(画像/MWS)。
2026年2月19日




きょうの画像は雲母薄片らしきもの。上から順に微分干渉,位相差,透過明視野,透過明視野+画像処理(ヒストグラム調整)です。コントラスト法が異なれば見えているものが変わるということを本ページでは繰り返し述べてきましたがその一例となっています。透過明視野ではほとんどコントラスト生成しないので使えない検鏡法と思ってしまうかもしれません。けれどもそれは大間違いです。透過明視野の画像をよく見ると黒い粒子が多数見えています。その部分だけ位相物体ではなく吸収物体です。微分干渉や位相差法ではこの吸収物体が判別できません。透過明視野+画像処理によって吸収物体が明瞭に判別できるとともに,雲母薄片の構造もかなり可視化されています(画像/MWS)。
2026年2月18日


いろいろなコントラスト法で物体を可視化できるのが顕微鏡法の特徴で強みでもあるのですが,このことをまったく理解せず,ひとつの検鏡法だけを使う人がいます。組織切片を検鏡する技師ならそれも正解です。各種染色法で染めた切片は透過明視野中央絞りで同じ条件で検鏡するのがスジでしょう。他方,どのような検鏡法が効果的なのかわからない未知の対象を覗く研究者としては,いろいろなコントラスト法を試すのがあるべき姿だと筆者は思います。
しかし現状では,微分干渉がよく見るのでそればかり使う人がいます。偏斜照明でじゅうぶんなのにわざわざ微分干渉をつかう人もいます。両者の像質の区別がついていないのです。顕微鏡は「見たい像を自分でつくる」光学的な装置でもあります。微分干渉の像は偏光干渉による被写界深度の浅い切片像で,位相差像とも透過明視野像とも偏斜の像とも異なるものです。像特性が異なるので,どちらかの1枚で何かを語ることは,光学を理解するまともな研究者なら避けるでしょう。
きょうの画像は海底堆積物から分離した珪藻被殻の薄片。画像1枚目は微分干渉によるもの。2枚目は位相差によるもの。両者ともに40倍対物,NA=0.65,照明はハロゲン+GIFです。どちらの画像も珪藻被殻にほかの珪藻被殻が重なった様子を余すことなく捉えています。
しかしほとんどの人は,きょうの画像1枚目に写っている重なった薄い被殻を見逃すことと思います。他方,きょうの画像2枚目に写っている重なった被殻は誰でも判別できると思います。これが微分干渉と位相差の違いです。研究者が好んで微分干渉を使うのは勝手ですが,像特性も理解せずに,見るべきものをわざと消していることにも気がつかない阿呆にならないようにと老婆心?を感じたりもするのです(画像/MWS)。
2026年2月17日

ふりかえってみるとなぜか当室への訪問客は大学教授,准教授,研究所の室長やリーダー,企業の社長といった職位の方々が多い感じです。まぁ当方が顕微鏡分野において「専門教育を行うことができる教員を育てる」ことを暗黙に目標としているのでその関係もあるかもしれません。
あるとき,水圏環境が専門の方が,こんど地球史をやるんですよね〜のようなことを仰るので,どこからやるの? 宇宙開闢? GUTから? と聞くと,晴れ上がりの辺りからやるとのこと。いやーさすがですね。地球の存在を語るには宇宙論は欠かせないのですから。
その先生がいつのまにか大学教員になっていて,こんどミミズの話をすることになったんですよね〜と仰るので筆者は,じゃ,まずはダーウインからだね,と返事をしたところ,その先生は,ダーウインはシラバスの1行目に書いたとのこと。そして先生のカバンからはダーウインの著作が出てきたのでした。さすがです。何がさすがなのかというと,ミミズが専門外でもすぐに外せない重要情報に行き当たりそれをコアに講義設計しているということ。こういった先生の受講生は幸せですね。
ウチに来訪する先生方はほぼこのレベルです。
きょうの画像は筆者手持ちのミミズの本ですが,ミミズの講義は20年以上前のむかし話になってしまいました。環境論の講義で,土壌保全がどれほど重要かを述べたときにミミズを登場させたのです。偏差値38の学生さんでしたがそんなことは関係ありません。数周後,「先生,干からびそうになったミミズを植え込みに戻して救助しました」などという若い学生の声を聞くと,何かは感じ取ってくれたんだなと思ったことでした。
ひるがえって筆者の学生時代を思い返すと,自分の専門でもない講義を任された教員が,付け焼き刃にすらなっていない中身のない講義で時間をつぶし,壮大な時間のムダが繰り広げられていたことに震撼します。その分野の基本図書も読んでいない。必要な物性も頭に入っていない。講義準備をしていないのは明白。ただの阿呆。お前の講義に出るよりも専門書でも読んでいた方が遙かにマシ。ふざけんな。
まだ20歳過ぎくらいの若者だったけれども,いやーオレが教卓で講義した方が100倍マシだわと思いながら爆発しそうになる感情をこらえながら耐えていました。じぶんが同じ年齢になって思うのですが,むかしの先生方はなんであんなに無責任だったのかほんとうに不思議です。あのダメな先生方を呼び出して今から口頭尋問したい気もします。人がわるいですねえ。わはは。
あ,念のため申し上げれば,すごい先生方もたくさんおられました。筆者の学位論文の主査副査は,一部を除けば,誰も文句をつけられない豪華メンバーでした。それだけでなく,内容的に不安な部分は自分で勝手にあこがれの先生に原稿を送って勝手査読してもらいました。お忙しいなかとてもていねいに対応して下さいました。先生方に貴重な時間をいただきほんとうに有り難いことと今でも思っております(画像/MWS)。
2026年2月16日


ひるメシを喰っていたら巨大なオナガダイのカブト・カマが入荷。本ページには沖縄関係者もご覧なのでアカマチと言った方がいいかしら。半割れでもずっしり。たぶん5kg以上,7,8kgのアカマチだろうと思います。しかも脂が乗っていて太っている。これは最高の食材なんですが価格は480円。鹿児島から運ばれてきてこれですからほぼ無料です。
アカマチってのは こんな 魚です。このお姉ちゃんめっちゃカッコイイ。こんな素敵な人が同時代に生きていると思うだけでなんか有り難い気もします。
こんなものが入荷しても筆者はまったく怯みません。まずはそのままでウロコを取ります。けっこうていねいに,取り切れないところは手でむしります。何しろ大きなウロコは2cmもあるのです。なぜそんなにていねいにウロコを取るのかというと,アカマチは皮がまたすばらしく美味なので,ウロコに邪魔されずに頬張りたいのです。
ウロコを落とせたら流水でざっと洗います。このとき血合いや傷みが早そうな部分をよく洗っておきます。そうしたら水をよく切ってから軽く塩を振ります。ウチでは男鹿の藻塩が標準です。これを冷蔵庫で数時間寝かせます。夕飯で食べたいので,入荷と同時に処理して冷蔵庫に入れれば夕方には数時間経過しているわけで好都合です。
数時間経過したら大きなフライパンに湯をわかします。沸いたら火を止めてそこに魚を投入。ぜんたいにまんべんなく湯をかけて20〜30秒。ずらしてフタをして湯を捨てます。これで表面の劣化層が除去されて薄く火が通り,残っていた鱗などが除去しやすくなります。このとき火が通った端っこをちぎって味見をします。薄い塩味が感じられるはずです。これをもとに調味料の量を決めます。
魚の入ったフライパンにぶつ切りのネギを放り込みます。しょうゆを適量,日本酒(一ノ蔵,辛口),水を加えます。強火でふわっと仕上げるので量は少ないです。フタをして強火で加熱します。フタを開けることなく最後まで強火で加熱して煮汁がなくなる直前で火を止めて数分おきます。これで完成。煮汁がほぼ見えませんが味がしっかり染みている煮魚のできあがりです。
きょうのアカマチがどれだけ大きいかは,画像2枚目の長ネギの太さと比べれば想像できるでしょう。そんなにふとくないネギではありますが,それでも比較するとアカマチがビッグサイズであることがわかるでしょう。
この大きさのアカマチのかぶと・カマ煮ははじめてで脳天が喜ぶおいしさで走って宮内庁に持っていきたいようなお味でした。ふわふわでしっとりした身質。ゼラチン質に富んだ目玉周辺や皮。プルプルとしたクチビルなど,食べ応えもありキンメダイのカブトを煮ているような人には上位互換かもしれません。この経験で価値観がよい意味で破壊され,オナガダイは刺身もいいけれども,タダみたいなアラがあったらそっちの方がいいよねと,たった1回の経験で思ったのでした。
沖縄ではアカマチのバター焼きが定番とのこと。そりゃ,そのままでもウマい魚をバター焼きにしたら飛び抜けた高級料理になるかもしれません。でも,個人的には,とくに魚の場合はウマいものにウマイを乗せるのは邪道かもしれないとも思っています。そのままでウマいんです。それを味わうのが本道です。筆者の砂糖食べない仲間の一人が,アカマチのことを,油に頼らなくても美味しいのに現地では油料理になってると仰っていたのが忘れられません。まったくその通りと思います。
それにしても不思議なのは,こういった食材が入荷すると自然に身体が動くこと。フンフン♪とこれはこうするとおいしいよねーと思いながら鱗をとったり洗ったり塩を振ったりして,何と一緒に煮ようかなー,ゴボウかなー,ネギかなー,ショウガかなーと思いながら,これだけ鮮度がよければショウガなしの方が白身の風味が生きるよね,加熱時間から見るとゴボウは却下かもね,じゃあ煮魚の煮汁をネギに吸わせよう,などとレシピが自動的に決まるのです。筆者の料理はいつもそうで,素材との対話で調理法が決まるので何かを参考に作ることは少ない感じです。
やっぱ進む道を間違えたかー。わはは(画像/MWS)。
2026年2月15日

おおまかな感じ,休日の昼間に雨が上がれば,そこから1〜2時間が散歩中のわんこに出会える確率が高いことが判明した気がする。若夫婦が可愛いわんちゃんを散歩中。この大都会でわんこと暮らすには持ち家が必須な気がしますが裕福なご家庭なのだろうか…。貧乏暮らしの筆者はわんこを拝ませてもらって有り難いのです(画像/MWS)。
2026年2月14日

なんて可愛いわんちゃん。ノーファインダーでの奇跡的な1枚。すれ違うときに手を振ったら飼い主さんが「ありがとうございます」。思わず「かっわいいですねー」と筆者。「ありがとうございます」と飼い主さん。このわんちゃんがとびきり可愛いのは飼い主さんの愛情が注がれているからなんですね(画像/MWS)。
2026年2月13日

ノーファインダーでの当てずっぽう撮影は想像できない,狙っては作れない絵になるのでやめられません…(画像/MWS)。
2026年2月12日



このところ2,3日,外出時間が減っていてうんどう不足気味だったので休日の午後は雨上がりをねらってカミさんと散歩。カルガモが忙しそうに昼食をとっているので見に行くとカワセミが枝にとまって獲物を探しています。何年ぶりかのカワセミだったので豆粒のような小ささでしたが見ほれて眺めていました。もちろん,豆粒でも撮影します。適当に撮影していたら,なんと獲物をねらって飛び込む瞬間や獲物を加えているところも写っていました。まだ平和が続く日本で,こんな休日の午後を過ごせる幸せを有り難いと思ったことでした(画像/MWS)。
2026年2月11日

ニコンS型顕微鏡時代の古い対物レンズのテスト。RGB分解撮影。対象はクモノスケイソウ化石種。このくらい見えれば日常のチェック用途にはじゅうぶんな主力戦力になりますね。たぶん筆者とほとんど同年代なんですが(画像/MWS)。
2026年2月10日


こんかいの衆院選について筆者は「中道のトップがまともかというとそんなことはなく,むしろ相場を読む力が壊滅的で,野党を破壊して焼け野原状態にする可能性を感じています」と予言しました。そして事実,その通りになりました。完全に焼け野原です。これは偶然でもなんでもなく,相場が読める人には当たり前の結果です。つまり何が言いたいのかというと,野田は途方もない阿呆で,その野田についていった党員も同じくらい阿呆だということです。野田を党首に据えている時点でこの政党は終わりが見えていたと思っています。
有権者のほとんどが政治に関心がなく,いつもどんな選挙でもほぼ人気投票や知っている名前を書くだけの,成熟した民主主義とはほど遠い状態というのが日本です。そんな中で,「中道」などという名前の政党の中身を正確に知っている有権者など100人に一人もいないでしょう。そして中道という名前が浸透するに十分な時間がない。本来なら数年は欲しいところ。加えて公明党を毛嫌いしている人は中道から離れていくでしょう。そんな簡単なこともわからないのです。
こういった阿呆と比較すると,テレビやスマホやパソコン画面に映し出される高市の方が遙かにマシに見えた方も大勢おられることと思います。まったくその通りかと思います。それで大統領選と勘違いしてか,高市を支持するために自民に投票した人も多かったことと想像します。
野田がリーダーとしてはどうしようもなくダメなのは政治通の間では常識に類することなんですが,なぜか政党の内部ではそういった声が届かない。これも不思議なことですね。今回の解散総選挙は奇襲攻撃に類するもので,とにかく時間がなかったので,「中道」を作らずにそのままの政党で選挙協力の形で対応したとしても,与党大勝は避けられなかったと思います。しかし当選できるはずの候補者が落選するといった事態は,いくらかは避けられたものと想像します。
小選挙区制は二大政党を仮定していて,この仮定が成立しなくなると,片方が大勝して片方は焼け野原になります。今回,立憲が名前を消して中道になり得体の知れない存在になり,しかも比例は公明が上から順にという取引で,もと立憲は自滅しました。もと公明は立憲分の票ももらって議席を増やしました。さすがは取引上手です。
今回は国民民主と参政党が候補者を山ほど立てたので票が分散し,これも小選挙区制では与党有利に働きました。国民民主は勝てないことがわかっていて候補者を擁立したものと想像しています。つまり票を分散させて中道を破壊することが主目的で,暗黙に自民の補完勢力であることを高市に示そうとしたのではと。前回の選挙でも同じ動きがありました。東京でいえば,国民民主が候補者を出さなければ,萩生田は落選したのです。
自民大勝でもよい政治を行いよい世の中に導いてくれれば,それは有り難いことです。しかし野党が減りすぎると都合の悪いことがあります。
国会の場での質問が減るのです。与党の政策について問題点を洗い出し国会で質問を行うことは議員の大事な仕事です。与党は都合の悪いことを隠そうとするので,それをごまかしのきかない国会の場でさらけ出し,いまこの国にはこのような問題が存在している,ということを知らしめるだけでも野党議員の存在価値があります。自民党裏金脱税議員や維新国保逃れの話を持ち出すまでもありません。これからこの国は,政府にとって不都合なことはますます隠される,という傾向が強まるかもしれません。
自民党と維新は利権政治を中心とした集合体です。これからは「責任ある積極財政」と言いながら,利権誘導型民主主義がさらに加速する懸念もあります。この利権優先政治は,確実に一部の国民にとっては有り難いものなので今回の与党大勝を喜んでおられる方々も多いことと思います。その一方で,利権誘導政治が国民一般を果たして豊かにするのかは未知数です。過去の与党の政治を見れば,消費税増税を繰り返し,社会保障費に充てるといいながら大企業の法人税減税に使われてきた実態があります。筆者の世代で見れば,入社時から給与が変わっていないといった声も聞かれます。さて,どうなりますかね。
今回はあまりにも自民が議席を増やしたのでもはや維新は不要になっています。そこの動きはちょっと面白そうですね。以前筆者が,政治家としては人間のクズと断じた吉村の阿呆が国保逃れ隠しのためか大阪都構想を掲げて意味のない府知事選をやらかしました。都構想は国も巻き込むおおごとなので自民は冷ややかにみているでしょう。高市が吉村をポイ捨てしてくれれば筆者的にはポイント高いですw あるいは飼い殺しでもいいです。わはは。
きょうの画像はそんな話題とは完全に関係のないワカサギのから揚げ。諏訪湖産です。ここ数年で食したおさかなの中で最高級魚じゃないかしら。内水面漁業はとっくの昔に崩壊していますが,趣味の釣りものが人づてに転がり込むことはあります。電気オーブンで2回チンしてからっとさせてうまし。藻塩,醸造酢,唐辛子で漬け込んだタマネギに放り込んで一晩。ウマいウマい!なのです(画像/MWS)。
2026年2月9日



そとを見ると雪もやんだのでカミさんとさんぽに外出。都心とは思えない冷気。そこいらへんの雪はやんでから数時間でもパウダースノー。八王子と東京都心にそれぞれ四半世紀住んできた経験からみてもこんな雪は見たことがない。15時でも解けないのは真冬日でもなければないはずで,温暖化やヒートアイランドの現代にあっては希少な現象に遭遇したのでした。
画像2枚目はカミさんが教えてくれた光景。筆者は何も気づかずに通り過ぎましたがカミさんが教えてくれて「おおっ」となりました。こういうの,中学生高校生くらいの頃なら見逃さなかったと思うのですがいまは中年オッサンですからねえー。
画像3枚目はn練馬区の気温記録。昼の最高気温が1゚Cに満たないのはきわめてレアな感じです。そんな気象的には異常な日に衆議院選挙が行われたのですね(画像/MWS)。
2026年2月8日

こんかいの解散総選挙はどこにも大義がありません。議会制民主主義の我が国は,総理が私でよいかを選んで欲しいと言ったところで,現総理の名前を書けるひとは奈良2区の住民だけ。ほぼ無意味。自分への人気投票を自民票へ誘導するだけの国民を欺いた選挙と言っても過言ではありません。
この総理のどこが良いのかなかなかわからないのですが,公明党との連立解消は政教分離という点からは評価してもよいと思っています。しかしながら,中国との関係悪化とその後の態度の硬直化は,一部のネトウヨどもは喜んでいるだろうけれども,実体経済を見るととても歓迎できません。日本が国際社会で生きのこる道は関係各国と良好な関係を維持することしかありません。食糧も,エネルギーも,金属も,レアアースも自給できない国なので。6000mの海底からレアアースを自給など,ほぼ宇宙開発なみの困難さです。
日本会議にどっぷりで統一教会とも癒着。言葉は勇ましいがその中身に対して責任はとらない。そして自分の言葉がまずくても絶対に撤回しない。絶対に謝らない。謝ったら死ぬ病にかかっているようです。そして不都合があれば人のせいにして被害者面をする。対応が面倒になったら逃げる。
NHKの日曜討論でも,衆院選期間中の唯一の党首討論なのに,大石あきこに統一教会問題を攻められるのを察知して病気を口実に逃げたように見えました。一国の総理が自分の判断で解散総選挙を打って出たのに,その意図を議論できる党首討論を欠席する。あり得ません。これを欠席するようなら総理の仕事もできないわけで,党首討論欠席=総理辞任に匹敵するようなことだと筆者は思います。
不要不急な解散で年度末予算の審議もできず,選挙の準備すらできない大雪の北陸,東北,北海道。受験シーズンに迷惑でしかない選挙演説の騒音。これだけ国民に迷惑をかける選挙も過去に例がない気がします。投票率が低いほど与党有利なのでわざと最悪な気象条件の投票スケジュールに設定しています。しかも解散から選挙までほぼ時間を与えないことで野党が結集することを防ぎ,国民に対しては考える時間を奪っています。国民も舐められたものです。
この総理を支持している人たちには何が見えているのでしょうか? 自民党から出てくる総理は自民党体質でしかなく,その自民党を支持しておられる方々が総理を支持するのならわかりますが,そこいらへんの一般人が総理を支持しているとすると,単なる印象による人気投票状態なのでしょうか? 総理の言葉は威勢がいいかもしれませんが,この人の過去の言動と行動を見ていると,言葉の責任をとるようには見えないし,世の中がよくなるようにも見えません。一例をあげれば,総理は2月4日の演説で「食料安全保障は、食糧自給率100%を目指す。日本の食品をどんどん海外にも輸出する」とぶちあげたそうです。実現するなら大変結構なことですが,脳みそ空っぽのオツムでなければこんな発言はまずできません。ただ思いつきを思考というプロセスを経ずに喋っているのです。そしてバカな国民がだまされる。やれやれです。
まぁ,そうかといって,総理経験者でもある中道のトップがまともかというとそんなことはなく,むしろ相場を読む力が壊滅的で,野党を破壊して焼け野原状態にする可能性を感じています。じゃあグラドルと不倫していた野党党首がまともかというと,言うことがころころ変わり,若者が喜びそうな言葉を並べているだけでどうしようもありません。ほかの野党にもそれほどの期待ができる状況ではありません。肝の据わったよい人材はいますがなぜか小規模政党にとどまっている人ばかりです。
つまり状況はこうです。現総理を支持して投票する人は過去30年茹でガエル状態になっていてその先が見えていない。いずれ茹でガエルになってお陀仏かもしれません。かといってこのままだと茹でガエルになってしまうと悟って野党に投票した結果は,湯船から出て吹雪にさらされてお陀仏かもしれません。
最後に一言。野党は魅力ある政策を出せという人がいますがそれはないものねだりです。野党のもっとも重要な仕事は与党がまともな仕事をしているか監視することです。裏金脱税,選挙買収,日本会議や統一教会との関係,消費税増税とセットになった法人税減税,社会保障費につかわれるはずの消費税が法人税減税の原資になっていること,いろんな問題があります。「野党は批判ばかり」と思っている人はすでに洗脳されてしまっています。与党は批判されるようなひどいことを組織的にやってきたわけで,そこを見ようとしない洗脳された国民は与党に洗脳されつづけて茹でガエルになるしかありません。
以上が毎日のように政見放送や国会,予算委員会などをラジオや動画で視聴している中年オッサンの意見です。きょうの画像は出先で咲いていた啓翁桜,けいおうざくらというそうで山形県の名産品のようです(画像/MWS)。
2026年2月7日

そこいらへんで売っている赤魚の干物。これをそのまま焼けば手間いらずで夕飯のおかずになるわけなんだけれども,筆者的にはそうはならないんですね。まず,鱗がついている。そのまま焼けば皮が食べられない。魚の皮というのはもっともウマい部分でもありこれを捨てるのは許せません。ので,ていねいに鱗を除去します。そうしたら皮目に本日の画像のような切り込みを入れて,まず身側を焼き,次に皮側を焼き,最後に少し火力をあげて軽く皮目に焼き目をつけます。スーパーに並んでいる特売品の干物でも,これで上等な酒のつまみ,ごはんのおかずになります。皮目の香ばしさを味わいつつ白飯を頬張るのもヨシ,熱燗をあおるのもヨシです。切り込みによって身離れもよくじつに食べやすくなります。こうして主夫料理は進化していくのです(画像/MWS)。
2026年2月6日


きょうの画像は雲母(たぶん)の薄片。雲母は分厚いものならマウントも容易ですが,珪藻被殻なみの薄いものとなるとサンプル調製が問題となります。海岸の砂などでサンプルが入手できたとしても,洗って乾燥させる段階で何かに貼り付いてしまい剥がすことが困難になります。歩留まりが悪いのです。そんな雲母を位相差とDICで撮影しました。両者で見えているものが異なるのが判別できるかと思います。段差を見るのか等高線を見るのか,そんな違いが画像にも現れています(画像/MWS)。
2026年2月5日

どの部分が親細胞で,どこが娘細胞で,どの順番に殻ができたのかわかるかな? ピンヌラリアの画像ですがいろんなことを示唆しているのです…(画像/MWS)。
2026年2月4日

きょうの画像はコスキノディスクスの微細構造。DICです。この構造はいろいろ多彩で電顕レベルのものから光学レベルまでいろいろあります。光学の場合は斜入射照明がもっとも高分解能で解像できますがそれなりにチューニングすればDICでもそこそこ見えます。どんな検鏡法で何がどこまで見えるか,その経験を蓄積するのも達人への道かもしれません(画像/MWS)。
2026年2月3日

なにげなく掲載している本ページの顕微鏡写真ですが,顕微鏡を使っている以上,対物レンズ直焦点?あるいはコンペンで補正?投影長は?鏡筒長は?拡大率は?などいろんなパラメータをいじることになります。現代のレンズにはそれに応じた使い方が,100年前のレンズにはその時代に応じた使い方があります。そこを押さえれば,むかしのレンズでも使える像になります。顕微鏡対物レンズは球面収差補正が命で,少なくともひとつの波長ではまともな像,つまりは開口数に見合った解像限界を示すように設計されているのです。スペック通りに解像しないのなら,壊れているか,使い方が間違っているのです。きょうの画像は50年くらいは経過していそうな古いレンズによるもの。投影系のマッチングに課題があるのか,それともこのレンズの軸上色収差補正の特性か,けっこう個性的な像です。鏡筒長はたぶん正しく,球面収差は小さいです(画像/MWS)。
2026年2月2日

このところいじっている顕微鏡がきょうの画像。オプチフォトDICの初期型です。DICスライダーにマッチした対物レンズの種類が少ないのが残念ではありますが,対物レンズごとにDICプリズムをそろえる必要がなく使い勝手はよろしいです。ベース部分には革を貼り付けて操作性を向上させています。革を貼り付けるだけでアタリがよくなり,冬場は手が冷やされることもなくなり,ほんとうに使い勝手が良くなります。なお寒い部屋で顕微鏡を扱うときは使用に先立って顕微鏡を日光の射し込む南側の部屋の窓際に置いて温めておきます。これによりグリスの硬化によるギアの破損を防ぐことができます(画像/MWS)。
2026年2月1日

1月31日はEU方面から来日中の先生と映像表現の専門家をお迎えして顕微鏡の午後でした。ここ2週間ほど微分干渉徹底追求トレーニングを行っていたので先生方にもDICの奥深さを体験いただきました。DICでは使用する光学素子,対物レンズの組合せで像はいくらでも変わります。同じ種類の対物レンズでも個体差で像が変わります。そういったことも考慮して可能な限りのチューニングを施したオプチフォトDICでパーフェクトな珪藻標本をご覧いただきました。鏡基が古いので1980年代の像ではありますが研究用途にじゅうぶん使えるレベルの高いものです(画像/MWS)。
Copyright (C) 2026 MWS MicroWorldServices All rights reserved.
(無断複製・利用を禁じます)
本ページへの無断リンクは歓迎しています(^_^)/
トップに戻る